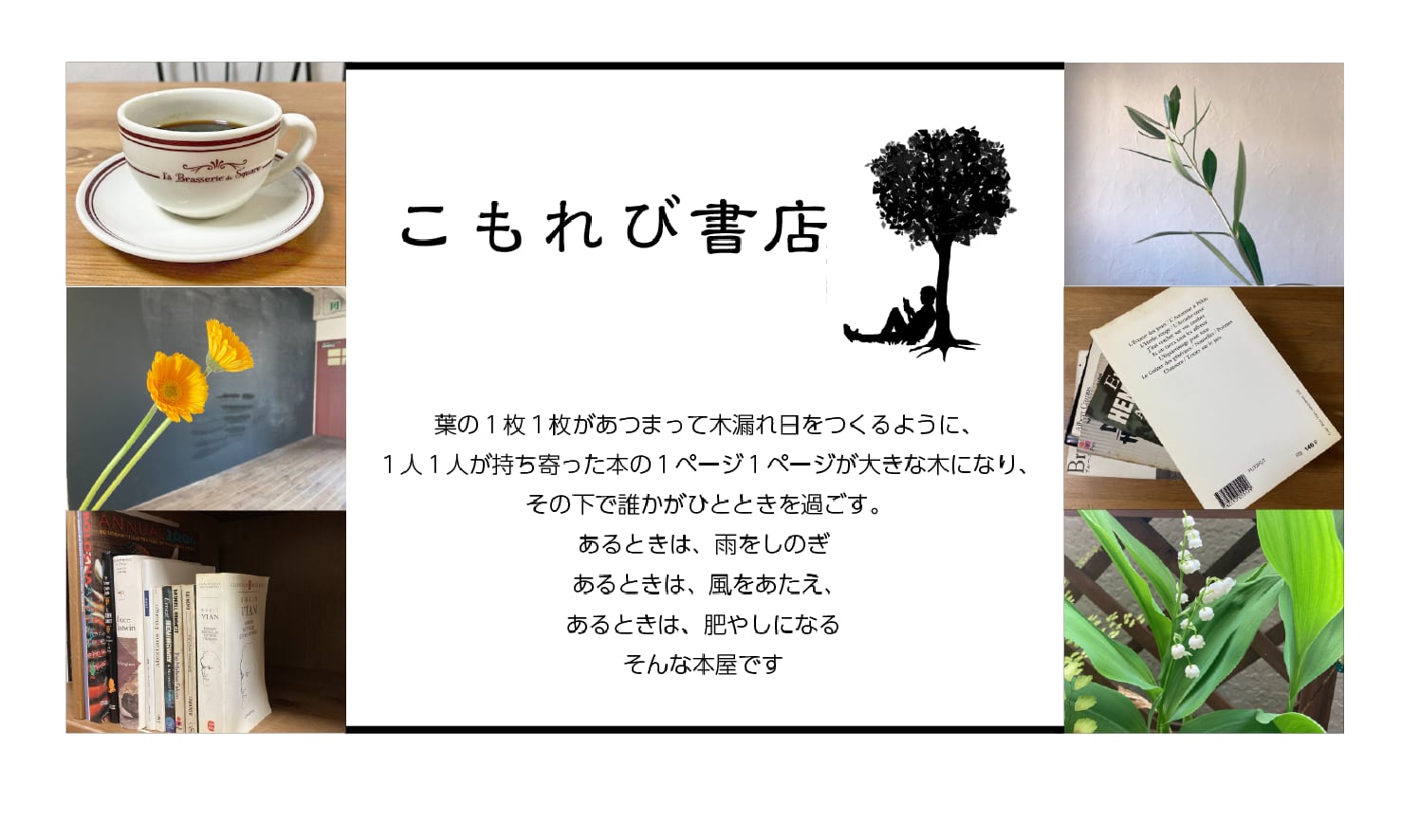通信販売
・こもれび書店では貸棚以外に、独自に選書した新刊も販売しています。古書はスタッフの書庫から放出したものです。
・店頭・在庫にないものは、お取り寄せもご相談ください。書名、出版社名を店頭、または問い合わせフォームでお知らせください。
・通販品切れのものは再入荷おしらせボタンを押しておいていただくと、仕入れの参考になります。
「店頭受け取りで購入した商品を「発送」に変更する場合は、〈参加チケット〉から〈追加送料〉を選んで、決済してください(合計A4/3cm厚以内に限ります)
-

神々の闘争 折口信夫論/ 安藤礼二
¥2,530
文庫 304ページ 2002年群像新人文学賞評論部門優秀作となった「神々の闘争――折口信夫論」を軸に、書き継ぎ推敲を重ねた論考が2004年にまとめられ、文芸評論家・安藤礼二の最初の単行本『神々の闘争 折口信夫論』となった。 その後の2008年に雑誌掲載された「『死者の書』という場(トポス)」という短い評論に作家・大江健三郎が目を留め、高く評価する。その出会いが2009年安藤礼二の『光の曼陀羅 日本文学論』(2016年に文芸文庫版を刊行)による大江健三郎賞の受賞につながっていく―― 折口信夫の文学と思想の源泉を探る問いかけは、やがて折口の生きた時代を共有した井筒俊彦、大川周明、北一輝、石原莞爾、西田幾多郎といった思想家たちの言葉を参照することにつながっていく。それは世界におけるアジア、アジアにおける日本を考えることにつながる。 第二次世界大戦以前の君主制日本、それは「天皇」の存在を抜きにして何かを考えることは不可能な時空間だが、そのような状況下での権力のあり様の本質を、昭和天皇の即位を契機に定義したのが折口信夫だった。 著者は論を進めるうち、やがて折口信夫の背後にある平田篤胤の神学の存在に至る。 折口信夫という孤高の文学者・思想家をその特殊性で理解するのではなく、つねに普遍性を備え同時代に生きて闘う存在ととらえる本書は単行本の刊行から20年を経て、新たに戦争状態が世界を覆っているかのように見える現在こそ読まれるべきなのかもしれない。 目次: 第一章 神々の闘争――ホカヒビト論 第二章 未来に開かれた言葉 第三章 大東亜共栄圏におけるイスラーム型天皇制 第四章 戴冠する預言者――ミコトモチ論 第五章 内在と超越の一神教 あとがき 初出一覧 補論 『死者の書』という場(トポス) 著者から読者へ 解説 斎藤英喜 年譜 著者自筆 送料の目安[40]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

宮本常一〈抵抗〉の民俗学 地方からの叛逆/門田岳久
¥3,300
四六判 420ページ 【版元サイトより】宮本常一は敗北したのか ポスト高度経済成長期の日本において、疲弊する離島の人びとに寄り添い、 彼らの自立を促すために奔走した宮本常一の思想や行動は 完全なる敗北だったのか。 たんなる民俗学者ではなく、地方の代弁者として活動した宮本常一の思想の核心に迫る。 柳田国男、南方熊楠、折口信夫と並ぶ民俗学界のビッグネーム——宮本常一。 本書では、斯界の巨人としてではなく、 当時広がっていた地域文化運動を構成する一個人としての宮本に着目し、 行政と地域住民とのあいだを取り持ち、運動を自律的なものへと導こうとした、 メディエーターとしての宮本常一に焦点をあて、 地方の代弁者として活動した宮本常一の思想の核心に迫る。 内容説明 柳田国男、南方熊楠、折口信夫と並ぶ民俗学界のビッグネーム宮本常一。本書では、斯界の巨人としてではなく、当時広がっていた地域文化運動を構成する一個人としての宮本に着目し、行政と地域住民とのあいだを取り持ち、運動を自律的なものへと導こうとした、メディエーターとしての宮本常一に焦点をあて、地方の代弁者として活動した宮本常一の思想の核心に迫る。 目次 序章 島の「遅れ」と文化運動 第1章 島をめぐるまなざし—学術・観光・地元 第2章 民俗学と「文化工作」のあいだ—宮本常一イントロダクション 第3章 「離島性」の克服—地域開発をめぐる宮本常一の思想的変遷 第4章 速度と身体性—フィールドワークの移動手段と見える世界の拡張 第5章 博物館と住民参加—「佐渡國小木民俗博物館」にみるローカルな文化運動 第6章 鬼太鼓座と幻の大学構想—日本海からの叛逆 第7章 自前の生活—佐渡空港建設をめぐるデモ・水・自己決定 第8章 三里塚から佐渡へ—ある運動家における民俗学的実践と“父” 第9章 モノを介したソーシャルデザイン—美大教員としての宮本常一と民家調査 結論 送料の目安[130]:3cm以上につきポストイン不可。 ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

宮本常一「忘れられた日本人」を読む/網野善彦
¥1,386
文庫判 254ページ 【版元サイトより】既存の日本像に鋭く切りこむ日本中世史家が,宮本常一の代表作『忘れられた日本人』を,用いられている民俗語彙に注目しながら読みぬき,日本論におけるその先駆性を明らかにする.歴史の中の老人・女性・子ども・遍歴民の役割や東日本と西日本との間の大きな差異に早くから着目した点を浮き彫りにし,宮本民俗学の真髄に迫る. 送料の目安[20]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

塩の道/宮本常一
¥1,012
文庫判 220ページ 【版元サイトより】生活学の先駆者として生涯を貫いた著者最晩年の貴重な話——「塩の道」、「日本人と食べもの」、「暮らしの形と美」の3点を収録した。日本人の生きる姿を庶民の中に求め、村から村へと歩きつづけた著者の厖大な見聞と体験がここにはある。日本文化の基層にあるものは一色ではなく、いくつかの系譜を異にするものの複合と重なりである、という独自の史観が随所に読み取れる本書は、宮本民俗学の体系を知るための最良の手引きとなるだろう。 「宮本先生は稀有のフィールドワーカーであった。山形県の酒田沖にある飛島に調査に行かれた時のことだという。何日か滞在して調査をすませ帰る時、港まで送ってくれた島の人が「先生は調査にきたといったのに、少しも調査しなかったが、良いんですか」と言ったという。「わしは見るものは見、聞くことは聞いて、久し振りに良い調査ができたと喜んで帰ったのだが……」と笑っておられたが、相手には調査をされたと感じさせないような調査だったのであろう。」(田村善次郎「解説」より) 送料の目安[20]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

別冊太陽 世界の呪術と民間信仰 国立民族学博物館コレクション/ 島村 一平 監修、 国立民族学博物館 特別協力
¥2,750
A4変型 160ページ 【版元サイトから】 ◎呪術に関わる研究の最前線がここにある! 人類にとって最も基層的な宗教現象である呪術と民間信仰。 その実践的な在り方を、みんぱくが所蔵する膨大なコレクションとともに紹介。 文化人類学者がめくるめく世界へと誘う。 巻頭言 みんぱくのコレクション 関 雄二 はじめに 呪的世界への旅 島村一平 《世界の呪術と信仰を旅する》 I オセアニア ドリーミング 平野智佳子/カヴァの杯 丹羽典生/ニューギニアの仮面 行木 敬 II 南北アメリカ 十字架と一面太鼓 岸上伸啓/アラスカの仮面 野口泰弥/メキシコのナワル 鈴木 紀 ニエリカ 山森靖人/エケコ 八木百合子 III ヨーロッパ ローラーとシェラー 森 明子/イースターエッグ 新免光比呂 ルーマニアの陽気な墓 新免光比呂/ストーリー・クロス 中川 理 IV アフリカ 呪物に覆われた狩人の衣装 吉田憲司/カラハリ砂漠の占いの道具 池谷和信 V 西アジア 猫の文字魔法 西尾哲夫/モフル 黒田賢治 アラビア文字の精神性 相島葉月、エモン・クライル VI 南アジア チベットの護符 森 雅秀/ラバーリーのミラー刺繍 上羽陽子 ナヴァラートリ祭礼 三尾 稔 VII 東南アジア バロンとランダが歩く村 吉田ゆか子/囲炉裏のカミさま 樫永真佐夫 オラン・アスリの精霊像 信田敏宏 VIII 朝鮮半島 魂が宿るモノのカタチ 神野知恵 IX 中国地域 回族の「都阿(dua)」 奈良雅史/毛沢東崇拝 韓 敏 X 中央・北アジア 呪力をもつ弦楽器 藤本透子/森の民の呪い 島村一平 森のシャーマンから現代のシャーマンへ 島村一平 XI アイヌ アイヌの信仰と呪術 齋藤玲子 XII 日本 鬼面の力 笹原亮二/天蓋 鈴木昂太 《小特集》 現代の魔女と呪い 河西瑛里子 予言する書 山中由里子 日本列島における鳥と呪術 卯田宗平 《通文化コラム》 貨幣から呪術まで 人に愛されてきたタカラガイ 池谷和信 呪具としての楽器 福岡正太 世界のしぐさとまじない 《読み物》 すべては『金枝篇』から始まった 伊藤亜和と歩く たのしいみんぱく モンゴル高原の呪的フィールドワーク 島村一平 『増殖するシャーマン』復刊記念トークイベント 島村一平、ゆる民俗学ラジオ 世界は“奇界”に満ちている 佐藤健寿 《寄稿》 呪いと薬 吉田憲司 《描き下ろし漫画》 呪いのゆくえ 都留泰作 《エッセイ》 混ざり成り、渦に祈る Apsu Shusei 私とみんぱく 伊藤亜和 送料の目安[100]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

漁民の芸術1 三浦半島の漁撈用具より
¥1,430
A5 70ページ 【版元サイトから】――民具から辿る海辺の郷土史 2023.10 神奈川の横須賀市自然・人文博物館が所蔵する漁撈用具(文化財)から、三浦半島の海辺の郷土史を辿る一冊です。 カラー写真や解説のほか、地元の元鮮魚店主や博物館学芸員へのインタビュー等も収録。 人と海が織り成す文化に触れる、きっかけとなれば幸いです。 編集 執筆 モリナヲ弥(サンズイ舎)
-

柳田国男自伝 故郷七十年・拾遺・補遺/柳田国男 、校注:石井 正己
¥2,046
文庫判 768ページ 【版元サイトから】生まれ育った家と家族、離れた故郷、読書遍歴と交友録、そして日本民俗学の歩み。「若い世代の人たち」のためにと談話筆記された「故郷七十年」「拾遺」に加え、その豊かな知的交流を物語る「補遺」24編を新たに収録。地図・系図・写真とともに、詳細な注を付した決定版。 送料の目安[不可]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

京都出町のエスノグラフィ -ミセノマの商世界- /有馬恵子
¥4,620
SOLD OUT
四六判 454ページ グローバル資本主義経済の末端で、小規模店舗はいずれ消滅すると考えられてきた。しかし本当にそうだろうか? 京都市北部の出町とよばれる「まち」で、店が営まれる空間(店の間:ミセノマ)をのぞき込んでみると、そこでは新しい試みが生まれ、人々が入り込み、まちは常に変化し続けている。 老舗の呉服店、流しの焼きいも屋、駅前のシェアサイクル……半径2kmから描きだされる濃密なフィールドワークから、まちのざわめきと響きあう声が聞こえてくる。 第1部 滅びゆくとされたものたちの思想に向けて 序章 ミセノマのアンサンブル 1 ミセノマと市場 2 通りとミセノマ 3 まちとミセノマ 4 商世界〈バザール・ワールド〉とミセノマ 1章 店、まち、アートのトリロジー 1 「滅びゆく店」「衰退するまち」という視点の再検討 1-1 自営業の両義性 1-2 まちのスキマとスキマ層 1-3 スポンジ化する都市 2 〈ミセノマのアート〉というパースペクティブ 2-1 空き間と空き家 2-2 クラブ的なミセノマとバザール的なまち 2-3 手で生みだされるものとしてのアートと社会的転回の時代における店 3 本書の目的と方法、対象と構成 3-1 目的と課題、方法 3-2 対象 3-3 構成 第2部 出町の誕生 2章 市場と工場 1 御土居と桝形 2 近代都市化とせめぎあい 2-1 米騒動と出町 2-2 闇市と出町 3 近代化と工業化 3-1 工場街と労働者 3-2 鐘淵紡績京都工場 3章 店を生き抜く——闘争から祭りへ 1 転換点 2 一九七〇年代 衝突——スーパー反対闘争 2-1 商店街の誕生と路上から消えゆく行商人 2-2 日本で最もスーパーの出店が難しいまち 2-3 出町と学生、若者文化 3 一九八〇年代 融合と分離――祭りの誕生と終焉 3-1 「出町広場」という祭りの誕生 3-2 祭りの終焉 3-3 生業の危機 4 一九九〇年代 アメとムチ——大店法の緩和とその見返り 4章 まちの物語とその書き換え 1 二〇〇〇年代 まちの物語——鴨川デルタ、神輿、鯖街道 1-1 まちづくりの流行と大学・専門家との協働 1-2 鴨川公園整備計画とワークショップ 1-3 まちづくりと喫茶店 1-4 伝統の神輿の復活 1-5 鯖街道——新しい伝統の物語 2 二〇一〇年代——まちのスポンジ化 2-1 商店街の衰退とスポンジ化 2-2 工場の撤退とまちのスポンジ化 Intermission ヒエログリフを読みほごす 第3部 出町のエスノグラフィ 5章 のれんを守る 1 呉服店 1-1 出町の呉服店 1-2 呉服店の商い 2 乾物店 2-1 出町の乾物店 2-2 店を支える 3 のれんとミセノマのスキマ 3-1 ミセノマのアンビバレンツ 3-2 ミセノマと老舗 6章 新しいのれん 1 KYOTOGRAPHIE 1-1 スキマを利用する 1-2 軒先に集う 1-3 まちにのれんを掛ける 1-4 商店街の日常的芸術実践 2 出町座 2-1 地域に密着した映画文化の復活 2-2 コロナ禍と映画館 2-3 出町座のカフェ 3 のれんとまちのスキマ 3-1 地と図 3-2 ARTとartが隣りあう 7章 穴場を形成する 1 駅前のシェアサイクル店 1-1 仕事場の獲得 1-2 穴場の発見——朽ち果てた建物 1-3 大家の困難 1-4 ママチャリの共有に見るクラフツマンシップと日常自転車文化 2 まちの喫茶店 2-1 喫茶you&me 2-2 新しくつくった古い喫茶店 2-3 「サキョウク的」コミュニティとリネン族 3 穴場とスキマの生態系 3-1 アーバントライブと交差性 3-2 遅れ、離脱、穴場 3-3 ニッチなアートと穴場の形成 8章 スキマに入り込む 1 喫茶店の間借り 1-1 コラボからの独立 1-2 シェアのシェア 2 倉庫を間借りした喫茶店 2-1 スーパーの倉庫を間借りする 2-2 コーヒー豆を選る 2-3 気遣いと承認 3 軒先の焼きいも屋 3-1 喫茶店と焼きいも 3-2 焼きいも屋のフロントヤードとバックヤード 4 受け継がれる技芸とまちのスキマ 4-1 ミセノマを可能にするための互酬関係 4-2 まちのスキマを耕す 9章 路上のミセノマで 1 ローカルな法解釈と地域のインフォーマルなルールの間で 2 流し売りの焼きいも屋 2-1 焼きいも屋を引き継ぐ 2-2 流し売りの技芸 2-3 物語のリメイク 3 路上の八百屋 3-1 出町のテキ屋と路上販売 3-2 八百屋が取り持つ共生関係 3-3 テキ屋と商店主、商店街組合の敵対関係と共生関係 3-4 路上を分かちあう——アルバイトの流儀 4 絡まりあう協働性と敵対性 4-1 路上を棲み分ける 4-2 アルバイトとクラブ 4-3 商人の野生 10章 まちの閾のあいだで——協働、敵対、黙認、撤退 1 路上をめぐる狡知と配慮 1-1 路上の賑わいと音 1-2 暗黙の共生関係 1-3 参入と撤退 2 ラストサムライ 2-1 「ジョー岡田」 2-2 ミセノマでのエキシビション 2-3 イカサマと婆娑羅 3 見世の間とバザール 11章 絡まりあう力としてのアート 1 魔力と通力 1-1 切麻を撒く 1-2 心の大文字 1-3 アートと力 2 見通す力と引き剥がす力 2-1 通力の交換と消滅 2-2 冬に思う夏の出町 3 間隙を縫う 3-1 書き換えと螺旋運動 3-2 打ち破る力としての破壊と、穴を穿つ力としての創造 3-3 互いの息の根をとめない 4 タンジブルなものとその力 終章 ミセノマのポリフォニー 1 ミセノマとまちのスキマで 1-1 「まち」からのパースペクティブ 1-2 「ミセノマ」からのパースペクティブ 1-3 「路上」からのパースペクティブ 1-4 穴とスキマの生態系 1-5 エピメテウスの挽回 2 ミセノマのスキマと余白 2-1 ミセノマとクラブ 2-2 バザールのスキマ、ミセノマの余白 2-3 ミセノマの商世界 3 重なりあうパルス おわりに 泡沫の栖 Epilogue 偶然のポリフォニー 送料の目安[不可]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

柳田国男と民俗学の近代 奥能登のアエノコトの二十世紀 /菊地暁
¥1,925
文庫 412ページ 【版元サイトから】「民間の新嘗祭」と呼ばれる奥能登のアエノコト。稲作民族の原点を伝えるとされるその姿は、じつは、激変する戦後日本の中で柳田国男とその門下たちによって「発見」されたものだった。フィールドとテクストに働く政治と修辞を徹底的に読み解き、アエノコトを「二十世紀の物語」として再考する。 序 章 奇妙な懸隔――柳田/民俗学というアポリア 第一章 闘争の場としての民俗文化財――宮本馨太郎と祝宮静の民俗資料保護 はじめに――民俗/学の再想像 一 起源としてのアチック 二 「民俗資料」の独立 三 民俗資料緊急調査の波紋 四 民俗文化財研究協議会の軌跡 おわりにかえて――そして「民俗文化」は「財」になる 第二章 あえのことのこと――小寺廉吉と四柳嘉孝の民俗調査 はじめに――ある儀礼像の創出 一 放浪の研究者――小寺廉吉の若山村調査 二 饗応の祭典――『歳時習俗語彙』から『山宮考』ヘ 三 分布と形態――四柳嘉孝のアエノコト調査 四 稲の産屋――にひなめ研究会と九学会連合能登調査 おわりにかえて――「民間の新嘗祭」の誕生 第三章 民俗と写真のあいだ――芳賀日出男と民俗写真 はじめに――民俗写真というプロブレマティック 一 写真家の民俗/民俗学者の写真 二 演出の否定――柳田国男の写真観 三 六枚目の写真――野本家のアエノコト 四 『田の神』へ至る道――芳賀日出男のアエノコト おわりにかえて――再び、民俗写真というプロブレマティック 第四章 農の心の現在――原田正彰とあえのこと保存会 はじめに――「文化の客体化」論再考 一 国指定重要無形民俗文化財――保存会設立まで 二 埋め込まれる太陽神――原田正彰の記述と調査 三 観光化の「希望」と「挫折」――植物公園のアエノコト実演 四 能登を越える――江戸村と国立歴史民俗博物館 五 伝承する現在――梅勝二さんと中谷省一さん おわりにかえて――それぞれのアエノコト 終 章 エスノグラフィック ノ セカイ 文献一覧 あとがき 岩波現代文庫版へのあとがき 解 説 索 引 送料の目安[30]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

風の人 宮本常一/佐田尾信作
¥2,200
A5判 196ページ 【版元サイトから】旅する民俗学者をめぐる人と時代の物語。中国新聞連載「生誕百年 宮本常一という世界」を改題、大幅加筆。赤坂憲雄(東北芸術工科大学東北文化研究センター所長)、稲垣尚友(竹大工・作家)、大矢内生気(全国離島振興協議会総務部長)ら7人へのロングインタビュウ収録。 送料の目安[40]: ネコポス(A4)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。ネコポスに入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

宮本常一と民俗学/森本孝
¥2,750
日本の伝記 知のパイオニア シリーズ A5・176ページ 玉川大学出版部 宮本常一の研究だけでなく、人物をも最も知っているといえる著者による一冊。 【版元サイトから】民俗学者・宮本常一は全国の農山漁村を歩いてまわり、古老たちの体験話を聞き記録しました。宮本の生涯を自分のことばで語ります。 送料の目安[60]: ネコポス(A4)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、ネコポスに入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください