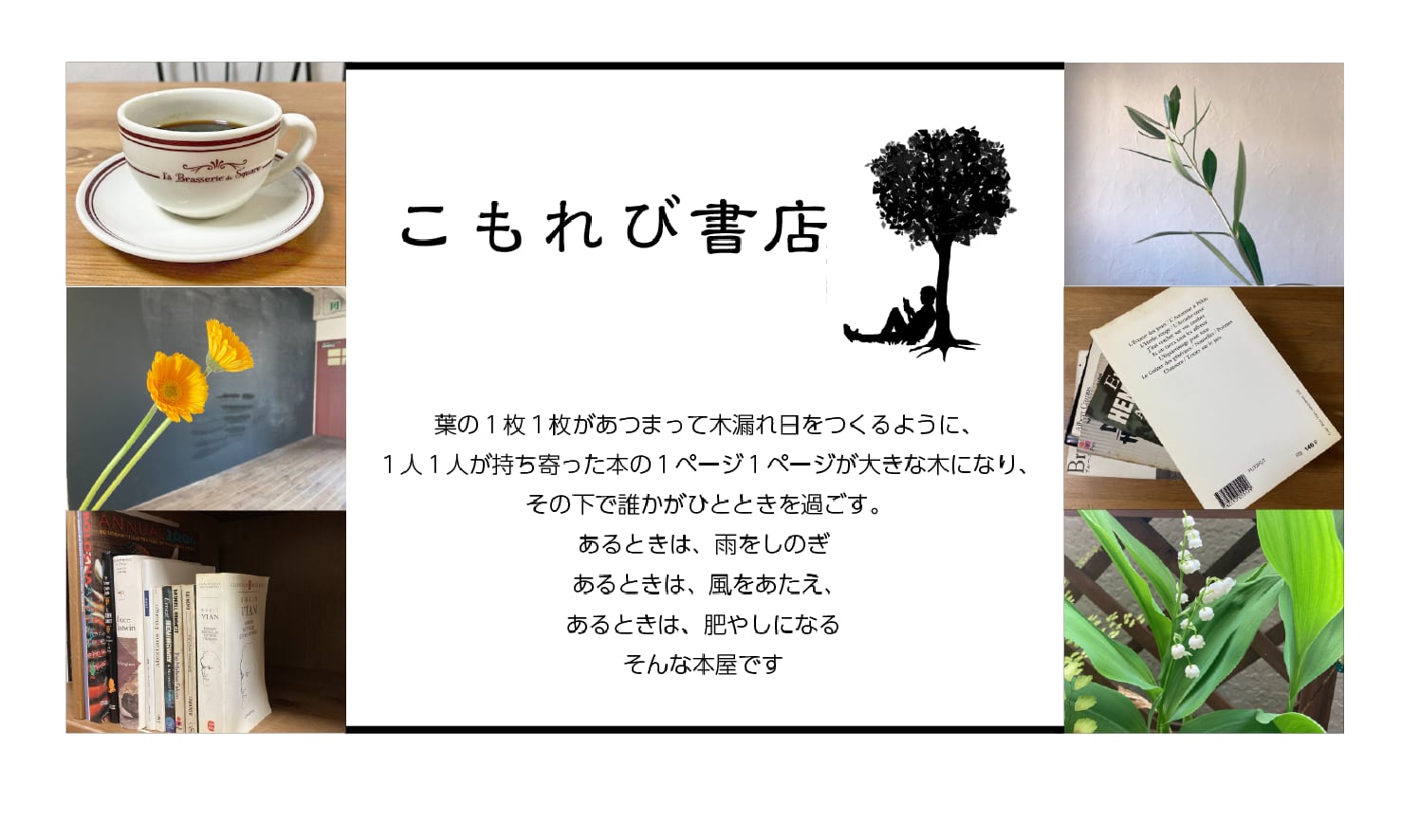通信販売
・こもれび書店では貸棚以外に、独自に選書した新刊も販売しています。古書はスタッフの書庫から放出したものです。
・店頭・在庫にないものは、お取り寄せもご相談ください。書名、出版社名を店頭、または問い合わせフォームでお知らせください。
・通販品切れのものは再入荷おしらせボタンを押しておいていただくと、仕入れの参考になります。
「店頭受け取りで購入した商品を「発送」に変更する場合は、〈参加チケット〉から〈追加送料〉を選んで、決済してください(合計A4/3cm厚以内に限ります)
-

星の古記録/斉藤国治
¥1,012
新書判 216ページ 【版元サイトより】東西の古い文献には日食・星食・流星・彗星などの数多くの天文記録が載せられている.今日,複雑な天文学的計算によって当時の状況を再現してみると,それらの記述が正確であるかどうかがわかる.著者は数々の記録の一つ一つを計算で確かめ,そのなかから興味深い話題を選びだし,昔の人たちが見た星空の世界へ読者を誘う. 送料の目安[30]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

ガンディー—秘教思想が生んだ聖人/杉本良男
¥1,078
新書判 336ページ 【版元サイトより】誰もが知る偉人マハトマ・ガンディーの「非暴力」思想はいかにして誕生したのか。インドの宗教思想に通暁した著者が、近年の新しい研究成果もふんだんに盛り込みつつ、なぜガンディーは今もって普遍的であり続けるのか、没後70年を期にその秘密を解き明かす。知られざるガンディーの若き日の活動や交遊関係をはじめ、当時傾倒していた20世紀初頭の秘教思想を中心とした思想潮流からの影響をたどり直し、その思想の根源を明らかにしようとする画期的評伝。 送料の目安[25]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

ユダヤの世界史—一神教の誕生から民族国家の建設まで/臼杵陽
¥2,860
四六判 424ページ 【版元サイトより】「民族」と「宗教」で世界の見方を深化させる。 「統一性」と「多様性」をあわせもつ、かくも豊かな歴史。 一神教の誕生、離散と定住、キリスト教・イスラームとの共存・対立、国際的ネットワークの展開、多彩な才能の開花、迫害の悲劇、国家建設の夢、現在の紛争・テロ問題……。 「本書はユダヤ人の歴史を世界史の流れの中で叙述したものである。ユダヤ人は民族集団あるいは信徒集団としての長い歴史をもっている。ユダヤ民族史を有史以来続くものとして描く立場さえもある。「ユダヤ四〇〇〇年の歴史」といった表現も人口に膾炙している。本書は私なりの立場からのユダヤ人あるいはユダヤ教徒の世界史である」(本書「はじめに」より) 「ユダヤ」の人々は数千年にわたって、信仰や記憶を通じて一つに結びついてきた一方で、自らが生きた時代や地域の中で、きわめて多様な姿を見せることとなった。 一神教の誕生から、離散と定住、キリスト教・イスラームとの共存・対立、国際的ネットワークの展開、多彩な才能の開花、迫害の悲劇、国家建設の夢、現在の紛争・テロ問題にいたるまで、そこにはこの世界の複雑さが映し出されてもいる。 「民族」であると同時に「信徒」である「ユダヤ人/教徒」の豊かな歴史を辿り、さらには、そこから逆照射して世界史そのものの見方をも深化させる。 送料の目安[130]: 3cm不可。ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

セット:食から知るイギリス
¥5,874
おすすめ理由や豆知識などを書いたペーパー付き! 『増補改訂 イギリス菓子図鑑 お菓子の由来と作り方 伝統からモダンまで、知っておきたい英国菓子135選』羽根則子 新たに30種類以上を加え、より多くのイギリス菓子について案内するのが、本書『増補改訂 イギリス菓子図鑑 お菓子の由来と作り方』です。 シュガークラフトやフードイベント、プディングの定義、フリー食品といったイギリスならではの菓子にまつわるエピソード、フランスやアメリカなど、ほかの国の菓子との関連についても言及し、イギリス菓子をテーマとした読み物としても楽しめます。 英国菓子文化を網羅したこの1冊は、イギリスや食に興味のある方も深く頷ける、イギリス菓子本の決定版です。 単品購入https://komorebibook.theshop.jp/items/114137340 『舌の上の階級闘争 「イギリス」を料理する』コモナーズ・キッチン パン屋と農家と大学教授の3人によるコレクティブ「コモナーズ・キッチン」が、料理を作って、食べて、考える! ベイクドビーンズ フィッシュ&チップス イングリッシュブレックファスト マーマレード ローストビーフ キュウリのサンドウィッチ …料理ごとに章立てされた12の食エッセイに、それぞれのレシピも収録。 まさに定番中の定番といえるイギリス料理の、歴史や文化的な背景を掘り下げながら、実際に作って食べてみることで、「階級」や「貧富の差」により分断された社会の現実を胃袋から思い知る! 単品購入https://komorebibook.theshop.jp/items/93746078 『砂糖の世界史』 川北稔 茶や綿織物とならぶ「世界商品」砂糖.この,甘くて白くて誰もが好むひとつのモノにスポットをあて,近代以降の世界史の流れをダイナミックに描く.大航海時代,植民地,プランテーション,奴隷制度,三角貿易,産業革命―教科書に出てくる用語が相互につながって,いきいきと動き出すかのよう.世界史Aを学ぶ人は必読! 単品購入https://komorebibook.theshop.jp/items/114137585 送料の目安[120]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

岡倉天心と思想/大久保喬樹
¥2,750
A5判 176ページ この伝記シリーズはルビがあるので、小学校中学年くらいから大人の学びにも。 【版元サイトから】岡倉天心は明治時代に日本初の美術学校をつくりました。貿易商の家に生まれ、子どものころから外国語の中で育ち英語の読み書きができました。西洋文化を理解した上で、インド、中国、日本の東洋文化の追及に励み、代表作『茶の本』を英語で書きました。外国で多くの人々に読まれ、西洋人に日本文化が知られるきっかけを作りました。 送料の目安[50]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

荻野吟子とジェンダー平等/堺正一
¥2,750
A5判 176ページ この伝記シリーズはルビがあるので、小学校中学年くらいから大人の学びにも。 【版元サイトから】荻野吟子は、明治時代、近代医師養成制度のもとで試験に合格して医師になった最初の女性です。さまざまな困難を乗りこえ、14年もかけてその道をきりひらきました。キリスト教とであって、社会活動にも力を注ぐようになりました。かたい信念のもと、苦しむ人びとに寄りそいつづけたその生涯を吟子自身が語ります。 送料の目安[50]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

ひろひと天皇年代記―一九四五年八月ヒロシマ/秦 恒雄
¥3,080
四六判 274頁 本書は、『原爆と一兵士』本文を影印復刻し、新たに注記・解説等を付したものになります。 【版元サイトから】 『原爆と一兵士』改題新装復刻版。セレクション名著復航第1弾。 それまで読み漁ってきた被爆体験記の類いとは一線を画する、ユニークな文体と重層的な内容に私は圧倒された。この埋もれた良書を読書界に知らしめるべく・・・(川本隆史「あとがき」より) 大竹海兵団に所属していた著者は、原爆投下の翌日、家族の待つ広島市内への帰休を許され、変わり果てた妻を目にする・・・。 想像絶するヒロシマの経験を、著者は30年の沈黙を経て、密かにその記憶を、自身の記憶を労るように、そしてその記憶をつなぐべく書き記していた。 透徹したまなざしと、つきはなしたような客観的な記述により、1945年8月のヒロシマを読者に追体験させる。 1980年に刊行された『原爆と一兵士』本文に、新たに注釈を付すとともに、 充実した解説・あとがきを加え、著者が原稿に付けたオリジナル・タイトルに戻し、被爆80年に刊行する。 送料の目安[50]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

別冊太陽 世界の呪術と民間信仰 国立民族学博物館コレクション/ 島村 一平 監修、 国立民族学博物館 特別協力
¥2,750
A4変型 160ページ 【版元サイトから】 ◎呪術に関わる研究の最前線がここにある! 人類にとって最も基層的な宗教現象である呪術と民間信仰。 その実践的な在り方を、みんぱくが所蔵する膨大なコレクションとともに紹介。 文化人類学者がめくるめく世界へと誘う。 巻頭言 みんぱくのコレクション 関 雄二 はじめに 呪的世界への旅 島村一平 《世界の呪術と信仰を旅する》 I オセアニア ドリーミング 平野智佳子/カヴァの杯 丹羽典生/ニューギニアの仮面 行木 敬 II 南北アメリカ 十字架と一面太鼓 岸上伸啓/アラスカの仮面 野口泰弥/メキシコのナワル 鈴木 紀 ニエリカ 山森靖人/エケコ 八木百合子 III ヨーロッパ ローラーとシェラー 森 明子/イースターエッグ 新免光比呂 ルーマニアの陽気な墓 新免光比呂/ストーリー・クロス 中川 理 IV アフリカ 呪物に覆われた狩人の衣装 吉田憲司/カラハリ砂漠の占いの道具 池谷和信 V 西アジア 猫の文字魔法 西尾哲夫/モフル 黒田賢治 アラビア文字の精神性 相島葉月、エモン・クライル VI 南アジア チベットの護符 森 雅秀/ラバーリーのミラー刺繍 上羽陽子 ナヴァラートリ祭礼 三尾 稔 VII 東南アジア バロンとランダが歩く村 吉田ゆか子/囲炉裏のカミさま 樫永真佐夫 オラン・アスリの精霊像 信田敏宏 VIII 朝鮮半島 魂が宿るモノのカタチ 神野知恵 IX 中国地域 回族の「都阿(dua)」 奈良雅史/毛沢東崇拝 韓 敏 X 中央・北アジア 呪力をもつ弦楽器 藤本透子/森の民の呪い 島村一平 森のシャーマンから現代のシャーマンへ 島村一平 XI アイヌ アイヌの信仰と呪術 齋藤玲子 XII 日本 鬼面の力 笹原亮二/天蓋 鈴木昂太 《小特集》 現代の魔女と呪い 河西瑛里子 予言する書 山中由里子 日本列島における鳥と呪術 卯田宗平 《通文化コラム》 貨幣から呪術まで 人に愛されてきたタカラガイ 池谷和信 呪具としての楽器 福岡正太 世界のしぐさとまじない 《読み物》 すべては『金枝篇』から始まった 伊藤亜和と歩く たのしいみんぱく モンゴル高原の呪的フィールドワーク 島村一平 『増殖するシャーマン』復刊記念トークイベント 島村一平、ゆる民俗学ラジオ 世界は“奇界”に満ちている 佐藤健寿 《寄稿》 呪いと薬 吉田憲司 《描き下ろし漫画》 呪いのゆくえ 都留泰作 《エッセイ》 混ざり成り、渦に祈る Apsu Shusei 私とみんぱく 伊藤亜和 送料の目安[100]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

「お静かに!」の誕生 近代日本美術の鑑賞と批評/今村信隆
¥2,970
SOLD OUT
四六判 456ページ 【版元サイトより】 果たして、人々の声はどこへ行ったのだろうか。 天皇皇后、エリート官僚、田舎客、赤門天狗、鷗外、白樺派...... 「沈黙」と「語らい」は歴史のなかでもせめぎ合う。 芸術と出会う場所、美術館。 「お静かに!」が生まれる空間で、鑑賞と批評の歴史を〈声〉や〈語らい〉から考える。 書かれることばと比べるとき、声を伴って話されることばは、いかにも不安定で、はかなく、頼りない。近代的な鑑賞と批評はそれぞれ、声と語らいを外側へと追いやることで、自らの輪郭を定めていったのではないか。 江戸から明治へと移り行く時期の「見世物」と「書画会・書画展会」の様子から、人々のあいだに線を引く近代的な博覧会、明治の演説文化に対する批評、雑誌『白樺』とその同人たちが求めた美術館の理想など、今日の鑑賞と批評の空間を再考する歴史的な事柄を取り上げ考える。明治期以降に次第に整えられていく鑑賞空間、批評空間はどのようなものだったのか。それは現在とどうつながっているのだろうか。 録音・録画が一般的になる以前の声や語らいを歴史的に問い直すことは簡単ではないが、歴史のなかのいくつかのポイントに的を絞り、エピソードを拾い集めるように解きほぐしていく。 〈沈黙〉と〈静けさ〉と、〈声〉と〈語らい〉。どちらが、より好ましいのか。あるいは、どちらがより「正しい」のか...ときに問われる現代のミュージアム。 いま、私たちの空間と声のあり方を見つめるために。 美術館だけではなく、図書館、劇場、コンサートホールなど、公共性のはざまで揺れながら考える人に。ぜひお読みいただきたい本です。「お静かに!」と言わざるを得ない環境に関わるすべての方に。 送料の目安【70】 厚みがあるため、A5判より大きな本(B5、A4など)と一緒にゆうパケット・ネコポスで送ることはできません
-

「玉音」放送の歴史学 -八月一五日をめぐる権威と権力-/ 岩田重則
¥2,640
四六判 300ページ 【版元サイトから】天皇の大恩か、権力の発動か 日本の近現代史のなかでもっとも有名なラジオ放送。ここで流された昭和天皇の声がアジア太平洋戦争終結を国民に告げた。この放送はなぜ必要だったのか。「御前」会議や原爆にかかわるメディアの報道、当時の人びとの肉声にいたるまでさまざまな文献資料を詳細にひもとくと、明治憲法体制における天皇とはいかなる存在か、そして「玉音」放送とはいったい何だったのかが明らかになる。これまで触れられてこなかった日本近代史の核心に迫る画期的著作。 [目次] はじめに 「聖断」と「玉音」放送の権力発動 権威による権力発動の隠蔽 明治維新と、「聖断」と「玉音」放送 第1章 天皇の権威と権力 第2章 戦争終結派の「国体護持」と昭和天皇「御親政」 第3章 皇居「正殿」全焼と「三種の神器」 第4章 「新型爆弾」と「原子爆弾」 第5章 ポツダム宣言受諾決定と「皇室は絶対問題也」 第6章 セットになった「国体護持」と「原子爆弾」 第7章 ポツダム宣言受諾「詔書」と「玉音」放送の演出 第8章 ポツダム宣言受諾「詔書」と「内閣告諭号外」を‟読む” 第9章 ラジオと新聞が誘導する「国体護持」 第10章 新聞が誘導する昭和天皇への懺悔と「国体護持」 第11章 「原子爆弾」報道の全面解禁 第12章 情報漏洩とうわさ話拡散 第13章 「御前」会議とは? 第14章 一億総懺悔とは? むすび あとがき 参考文献 人名索引 送料の目安[30]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[50]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

ひめゆりたちの春秋 ー沖縄女師・一高女の「寄宿舎」ー/仲程昌徳
¥1,650
新書判 181ページ 【版元サイトから】1916年「ひめゆり学園」寄宿舎が落成してから、1945年3月22日、最後の留送別会がおこなわれるまでの出来事。 やがて悲惨な戦争に巻き込まれていく「ひめゆりたち」の青春の日々。 「寄宿舎についての「ひめゆり学徒」たちの話を聞きながら、彼女たちにも青春の楽しい思い出があったことを嬉しく思った。寄宿舎を取り上げた、大きな理由である。 ひめゆりたちの姿が、少しでも伝わってくれたらと思う。」(本書「あとがき」より) ■目次 はじめに Ⅰ、寄宿舎へようこそ Ⅱ、寄宿舎の始まりと事件 Ⅲ、大正期の寄宿舎生活と団欒 Ⅳ、社会情勢の変化と寄宿舎 Ⅴ、しのびよる軍国化 Ⅵ、太平洋戦争への道 Ⅶ、戦時下の行事と楽しみ Ⅷ、十・十空襲をくぐり抜けて Ⅸ、一九四五年の寄宿舎 Ⅹ、「ひめゆり学徒隊」として おわりに 附・『姫百合のかをり』再見 あとがき 送料の目安[30]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

蓬莱の海へ 台湾二・二八事件 失踪した父と家族の軌跡/ 青山惠昭
¥2,420
四六判 304ページ 【版元サイトから】父は「台湾二・二八事件」の犠牲者だった 与論島 台湾島 沖縄島 非情な歴史の記憶と、国境をこえる人々の心のつながりを描く、個人的かつ歴史的なノンフイクション。 歴史の波に翻弄された家族の記憶と、外国人ではじめて「台湾2・28事件」犠牲者として、認定賠償が認められるまでの記録。 沖縄から問い直す、台湾、日本の知られざる現代史 著者より 「自分史」を書こうと考えたのではありませんが、自らのまわりで起きた大事なこと、子や孫に伝えないといけないことを残しておくことを思い立ち4年前から書き記してきました。 文章力もなく知識も浅いなかで七転八倒の連続でしたが、ただただ恐れを知らない〝使命感〟におされて粉骨邁進、今ようやく発刊の時がきました。」 目次 はじめに 父は「台湾二・二八事件」の被害者だった 第一部 台湾二・二八事件と漂流家族 第一章 事件発生と父の失踪 第二章 与論島生まれ 第三章 基隆社寮島物語 【コラム】佐藤春夫の「社寮島旅情記」 第四章 彷徨の海 【コラム】沖縄復帰祈願海上大会 第二部 失踪宣告と逆転勝訴 第五章 失踪宣告 第六章 台湾の島を歩く 第七章 法廷へ 第八章 逆転勝訴 第九章 認定賠償を実現して 【コラム】西村京太郎、二・二八事件を書く 第三部 台湾と沖縄の未来へ 第十章 沖縄関係被害者 第十一章 台湾人船主の「證文」 第十二章 歴史を記憶すること 第十三章 沖縄と台湾、そして日本 送料の目安[60]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

帝国の書店 書物が編んだ近代日本の知のネットワーク /日比嘉高
¥5,940
A5 414ページ 【版元サイトから】かつて日本の勢力圏には、多くの書店が存在した。そうした「外地」書店と、そこへ書物を運んだ取次業者は、出版の中心たる内地と、他民族を含む外地の読者を結びつけ、流通網を形成した――。書店人の個人史を織り交ぜながら、帝国日本全域の取次・書店史を編み、人と知の移動を支えた文化的基盤の全貌を浮かび上がらせる。 凡例・参考地図 はじめに──外地書店からみえる帝国の人と知の風景 Ⅰ 書店網を見わたす──空間支配と知のインフラストラクチャ 第1章 帝国の書物ネットワークと空間支配──マリヤンの本を追って 第2章 外地への書店進出の歴史──書籍雑誌商組合史と小売書店の誕生から 第3章 帝国の書物取次──大阪屋号書店、東京堂、関西系・九州系取次など Ⅱ 近代東アジアの日本語書物流通──台湾、朝鮮、満洲、中国 第4章 新高堂と日本統治下の台湾書店史 第5章 朝鮮半島における日本語書店と書物取次ネットワーク 第6章 満洲の本屋たち──満洲書籍配給株式会社成立まで 第7章 中国で本を買う──華北、華中における日本人居留民と書店 Ⅲ 移植民地の書店──北南米、樺太、南洋 第8章 日本人街に本屋を開く──北米南米の日系移民と日本語書店 第9章 北方植民地の本屋──樺太における日本人書店史 第10章 南方共栄圏の書店と書籍配給 Ⅳ 戦争と書店──統制、配給、引揚げ 第11章 統制経済と書物流通──共同販売所から国策書籍配給会社へ 第12章 戦時下における内地外地の小売書店──企業整備、共同仕入体、読者隣組 第13章 本屋の引揚げ、本の残留 おわりに──そしてまた本屋を開いた 注 主要参考文献一覧 初出一覧 あとがき 人名索引 送料の目安[不可]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

京都出町のエスノグラフィ -ミセノマの商世界- /有馬恵子
¥4,620
SOLD OUT
四六判 454ページ グローバル資本主義経済の末端で、小規模店舗はいずれ消滅すると考えられてきた。しかし本当にそうだろうか? 京都市北部の出町とよばれる「まち」で、店が営まれる空間(店の間:ミセノマ)をのぞき込んでみると、そこでは新しい試みが生まれ、人々が入り込み、まちは常に変化し続けている。 老舗の呉服店、流しの焼きいも屋、駅前のシェアサイクル……半径2kmから描きだされる濃密なフィールドワークから、まちのざわめきと響きあう声が聞こえてくる。 第1部 滅びゆくとされたものたちの思想に向けて 序章 ミセノマのアンサンブル 1 ミセノマと市場 2 通りとミセノマ 3 まちとミセノマ 4 商世界〈バザール・ワールド〉とミセノマ 1章 店、まち、アートのトリロジー 1 「滅びゆく店」「衰退するまち」という視点の再検討 1-1 自営業の両義性 1-2 まちのスキマとスキマ層 1-3 スポンジ化する都市 2 〈ミセノマのアート〉というパースペクティブ 2-1 空き間と空き家 2-2 クラブ的なミセノマとバザール的なまち 2-3 手で生みだされるものとしてのアートと社会的転回の時代における店 3 本書の目的と方法、対象と構成 3-1 目的と課題、方法 3-2 対象 3-3 構成 第2部 出町の誕生 2章 市場と工場 1 御土居と桝形 2 近代都市化とせめぎあい 2-1 米騒動と出町 2-2 闇市と出町 3 近代化と工業化 3-1 工場街と労働者 3-2 鐘淵紡績京都工場 3章 店を生き抜く——闘争から祭りへ 1 転換点 2 一九七〇年代 衝突——スーパー反対闘争 2-1 商店街の誕生と路上から消えゆく行商人 2-2 日本で最もスーパーの出店が難しいまち 2-3 出町と学生、若者文化 3 一九八〇年代 融合と分離――祭りの誕生と終焉 3-1 「出町広場」という祭りの誕生 3-2 祭りの終焉 3-3 生業の危機 4 一九九〇年代 アメとムチ——大店法の緩和とその見返り 4章 まちの物語とその書き換え 1 二〇〇〇年代 まちの物語——鴨川デルタ、神輿、鯖街道 1-1 まちづくりの流行と大学・専門家との協働 1-2 鴨川公園整備計画とワークショップ 1-3 まちづくりと喫茶店 1-4 伝統の神輿の復活 1-5 鯖街道——新しい伝統の物語 2 二〇一〇年代——まちのスポンジ化 2-1 商店街の衰退とスポンジ化 2-2 工場の撤退とまちのスポンジ化 Intermission ヒエログリフを読みほごす 第3部 出町のエスノグラフィ 5章 のれんを守る 1 呉服店 1-1 出町の呉服店 1-2 呉服店の商い 2 乾物店 2-1 出町の乾物店 2-2 店を支える 3 のれんとミセノマのスキマ 3-1 ミセノマのアンビバレンツ 3-2 ミセノマと老舗 6章 新しいのれん 1 KYOTOGRAPHIE 1-1 スキマを利用する 1-2 軒先に集う 1-3 まちにのれんを掛ける 1-4 商店街の日常的芸術実践 2 出町座 2-1 地域に密着した映画文化の復活 2-2 コロナ禍と映画館 2-3 出町座のカフェ 3 のれんとまちのスキマ 3-1 地と図 3-2 ARTとartが隣りあう 7章 穴場を形成する 1 駅前のシェアサイクル店 1-1 仕事場の獲得 1-2 穴場の発見——朽ち果てた建物 1-3 大家の困難 1-4 ママチャリの共有に見るクラフツマンシップと日常自転車文化 2 まちの喫茶店 2-1 喫茶you&me 2-2 新しくつくった古い喫茶店 2-3 「サキョウク的」コミュニティとリネン族 3 穴場とスキマの生態系 3-1 アーバントライブと交差性 3-2 遅れ、離脱、穴場 3-3 ニッチなアートと穴場の形成 8章 スキマに入り込む 1 喫茶店の間借り 1-1 コラボからの独立 1-2 シェアのシェア 2 倉庫を間借りした喫茶店 2-1 スーパーの倉庫を間借りする 2-2 コーヒー豆を選る 2-3 気遣いと承認 3 軒先の焼きいも屋 3-1 喫茶店と焼きいも 3-2 焼きいも屋のフロントヤードとバックヤード 4 受け継がれる技芸とまちのスキマ 4-1 ミセノマを可能にするための互酬関係 4-2 まちのスキマを耕す 9章 路上のミセノマで 1 ローカルな法解釈と地域のインフォーマルなルールの間で 2 流し売りの焼きいも屋 2-1 焼きいも屋を引き継ぐ 2-2 流し売りの技芸 2-3 物語のリメイク 3 路上の八百屋 3-1 出町のテキ屋と路上販売 3-2 八百屋が取り持つ共生関係 3-3 テキ屋と商店主、商店街組合の敵対関係と共生関係 3-4 路上を分かちあう——アルバイトの流儀 4 絡まりあう協働性と敵対性 4-1 路上を棲み分ける 4-2 アルバイトとクラブ 4-3 商人の野生 10章 まちの閾のあいだで——協働、敵対、黙認、撤退 1 路上をめぐる狡知と配慮 1-1 路上の賑わいと音 1-2 暗黙の共生関係 1-3 参入と撤退 2 ラストサムライ 2-1 「ジョー岡田」 2-2 ミセノマでのエキシビション 2-3 イカサマと婆娑羅 3 見世の間とバザール 11章 絡まりあう力としてのアート 1 魔力と通力 1-1 切麻を撒く 1-2 心の大文字 1-3 アートと力 2 見通す力と引き剥がす力 2-1 通力の交換と消滅 2-2 冬に思う夏の出町 3 間隙を縫う 3-1 書き換えと螺旋運動 3-2 打ち破る力としての破壊と、穴を穿つ力としての創造 3-3 互いの息の根をとめない 4 タンジブルなものとその力 終章 ミセノマのポリフォニー 1 ミセノマとまちのスキマで 1-1 「まち」からのパースペクティブ 1-2 「ミセノマ」からのパースペクティブ 1-3 「路上」からのパースペクティブ 1-4 穴とスキマの生態系 1-5 エピメテウスの挽回 2 ミセノマのスキマと余白 2-1 ミセノマとクラブ 2-2 バザールのスキマ、ミセノマの余白 2-3 ミセノマの商世界 3 重なりあうパルス おわりに 泡沫の栖 Epilogue 偶然のポリフォニー 送料の目安[不可]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

砂糖の世界史/ 川北稔
¥1,034
新書 212ページ 【版元サイトから】茶や綿織物とならぶ「世界商品」砂糖.この,甘くて白くて誰もが好むひとつのモノにスポットをあて,近代以降の世界史の流れをダイナミックに描く.大航海時代,植民地,プランテーション,奴隷制度,三角貿易,産業革命―教科書に出てくる用語が相互につながって,いきいきと動き出すかのよう.世界史Aを学ぶ人は必読! プロローグ 砂糖のふしぎ 第1章 ヨーロッパの砂糖はどこからきたのか 第2章 カリブ海と砂糖 第3章 砂糖と茶の遭遇 第4章 コーヒー・ハウスが育んだ近代文化 第5章 茶・コーヒー・チョコレート 第6章 「砂糖のあるところに、奴隷あり」 第7章 イギリス風の朝食と「お茶の休み」──労働者のお茶 第8章 奴隷と砂糖をめぐる政治 第9章 砂糖きびの旅の終わり──ビートの挑戦 エピローグ モノをつうじてみる世界史──世界史をどう学ぶべきか あとがき 送料の目安[30]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

室町時代の祇園祭/河内 将芳
¥1,980
四六判 248ページ 【版元サイトから】京都祇園祭の歴史上、最も盛大であった室町期の祇園祭(祇園会)に注目し、公武権力が京都に併存した室町期ならではの特徴を解明。 はじめに 室町時代京都の祇園祭/河東の祇園社/洛中(上京と下京)/武家と公家/比叡山延暦寺 第一章 室町時代の神輿渡御 1 神輿と御旅所 三基の神輿/大政所御旅所/少将井御旅所/先祖助正/御旅所神主と馬上役/馬上一衆・合力神人制/馬上御鉾十三本、神馬五疋/神輿に供奉/馬上役が下行されない人びと 2 神幸路と駕輿丁 南門前の三鳥居/浮橋/堀川神人/神幸路/京極大路/三条大宮/大宮駕輿丁/師子を罪科に/喧嘩の実態/神がのる輿/蛤商人、今宮神人 第二章 室町時代の風流と山鉾巡行 1 風流 馬長/山の登場/風流としての山/定鉾/風流としての定鉾/久世舞車/笠鷺鉾(鵲鉾)/一四日の風流としての笠鷺鉾(鵲鉾) 2 山鉾巡行 京中鉾/下辺の鉾/『祇園会山鉾事』/六〇基の山鉾/山鉾の所在地/同じ所在地の山鉾/綾小路町四条間の船/笠/四条大路、三条大路を渡る/巡行路/『月次祭礼図?風』(模本)に描かれた祇園会/乗牛風流/牛背/室町時代の風流と山鉾巡行 第三章 祇園祭と室町時代の武家・公家 1 武家の祇園会見物 足利尊氏の祇園会見物/足利義詮の祇園会見物/見物と触穢/足利義満の祇園会見物/室町殿(足利家の家督)の祇園会見物/足利義持の祇園会見物/足利義教の祇園会見物/祇園会見物をしなかった足利義勝/足利義政の祇園会見物/式日の混乱/義教を先例とする/山鉾巡行の混乱/戦国時代の先例となった義政の御成・見物/義持による見物の重要性 2 公家の祇園会見物 公家衆の祇園会見物/後小松上皇・称光天皇の祇園会見物/後小松上皇の御所望/仰せと所役/北畠笠鷺鉾と大舎人鉾の推参/棧敷を構えず見物する/後花園天皇の御所望/祇園会と延暦寺大衆 第四章 伝えられた室町時代の祇園会 1 山口祇園会、津和野祇園会 在京する武士たちの祇園会見物/山口祇園会/『山口祇園会毎年順勤人数之事』/大内盛見の在京/技能が必要とされた「鷺の舞」/津和野祇園会/鷺舞の式をあらためて習い来たる/左義長を囃す大黒/室町時代の息吹を伝える 2 南都祇園会 祇園社の勧請/南都祇園会のはじまり/南都祇園会の風流/山・舞車・笠/舞車相論と探取/探を取らない手?郷/失われた南都祇園会 おわりに 祇園会の再興/なぜ明応九年に再興されたのか/中京火事と神勅/三十三箇年/恠異と奇跡 関係略年表/【参考文献】・【図版出典一覧】/あとがき 送料の目安[60]: ゆうパケットまたはネコポス(A4/3cm)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください
-

安倍晴明の一千年「晴明現象」を読む/田中 貴子
¥1,320
SOLD OUT
文庫 250ページ 法藏館 【版元サイトから】怨霊都市平安京を護るスーパー陰陽師・安倍晴明。そのイメージはいかにして誕生したのか。平安時代に一官人として生きた晴明が、時代と世相にあわせて変貌し続ける「晴明現象」を追い、晴明に託された人々の思いを探る好著。 送料の目安[30]: ネコポス(A4)1通で送れるのは合計[120]までとお考えください。お買い物の組み合わせにより、ネコポスに入らない場合はこちらで適宜、レターパックや宅配便に送料を修正してお送りします。あくまで目安とお考えください